目次
はじめに
「B型就労だけで生活は成り立たない。老後資金なんて夢のまた夢」
──そんな声を現場で聞くことが増えています。特に障害基礎年金が受給できない層にとって、月1万円前後の工賃では生活どころか、貯蓄の余地すらありません。
この問題の根底にあるのは、福祉事業所の構造的な搾取と、給付金の使途に対する不透明性です。そしてなにより、「まず現金給付が生活の基盤」という視点が、日本の福祉政策には決定的に欠けていることです。
■ 月1万円の工賃 vs 事業所への月15万円の給付
多くの就労継続支援B型事業所では、利用者の工賃が月1〜2万円程度であるのに対し、事業所が国から得ている給付金は一人当たり月約15万円前後と言われています。
この差額は、事業所の運営費、人件費、施設費などに使われているとされますが、利用者にとっての実益はあまりにも小さく、「事業所が労働力を搾取している」との批判が後を絶ちません。
■ 現金給付と居場所支援の“両立”がなぜできないのか?
本来、「居場所支援」と「生活の安定(現金)」は両立可能なはずです。しかし、多くの事業所は「居場所の提供」を前面に出し、それだけで役割を果たしたかのような体裁を取っています。
けれども、精神的安定も自己肯定感も、まずは経済的な基盤があってこそ。現金給付を受けられれば、「働けるときに働きたい」という自然な気持ちも生まれやすくなるのです。
■ 海外モデルに学ぶ:「現金給付+選べる支援」
アメリカ:
低所得の障害者に対して毎月約900ドル(約13万円)のSSI(障害者所得保障)を給付。居場所や支援施設の利用はあくまで本人の選択であり、支援と経済基盤は明確に分けられています。
北欧諸国:
スウェーデンなどでは、「障害があっても市民としての標準的な生活を営めるように」という視点から、月15万円前後の現金給付+住宅手当があり、生活基盤は常に国が支えています。
ドイツ:
就労支援施設には法的監査があり、給付金の使途は利用者にも開示されます。報酬も工賃という名目ではなく、労働の対価として扱われています。
■ 提案:非課税の現金給付+透明な運営
制度改正があるとすれば、以下のような仕組みを提案したいです。
事業所をREIT的な非課税モデルにする
→ その代わりに、国からの給付金の90%を利用者に直接現金で還元
事業所には1人あたり月1万円の運営費だけが入る構造にする
→ 搾取インセンティブを排除し、居場所提供が“本当に必要な事業者”のみが残る仕組みに
■ 最後に:このままでは、生活保護しか道がなくなる
障害年金を受け取れず、B型就労しか選べない人にとって、老後どころか目の前の生活も破綻寸前です。現状では生活保護しか道が残されていないケースも多く、「支援しているはずが依存を増やしている」という皮肉な構図になっています。
本当に必要なのは、“働かせる”ことではなく、“安心して生きられる土台をつくる”こと。そのために、まず現金給付の拡充と透明な制度設計が急務です。
■ 免責事項
※本記事の内容は、執筆者の調査および見解に基づいたものであり、すべての制度や実例に当てはまるものではありません。実際の支援制度の利用や制度改革に関する判断は、自治体や専門機関にご確認ください。また、記事内で紹介する海外事例は参考情報として掲載しており、日本国内の制度とは異なる点が多く存在します。
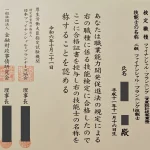

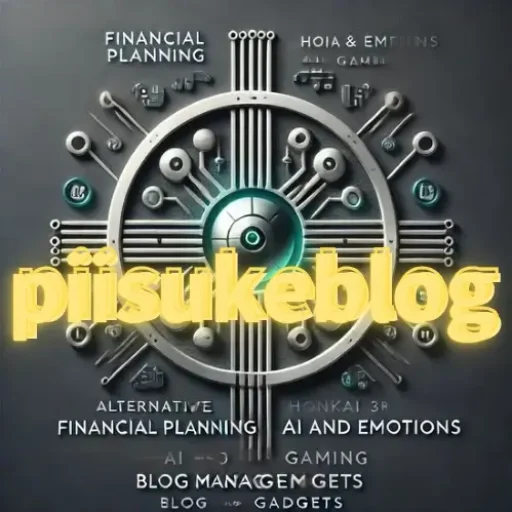

コメント